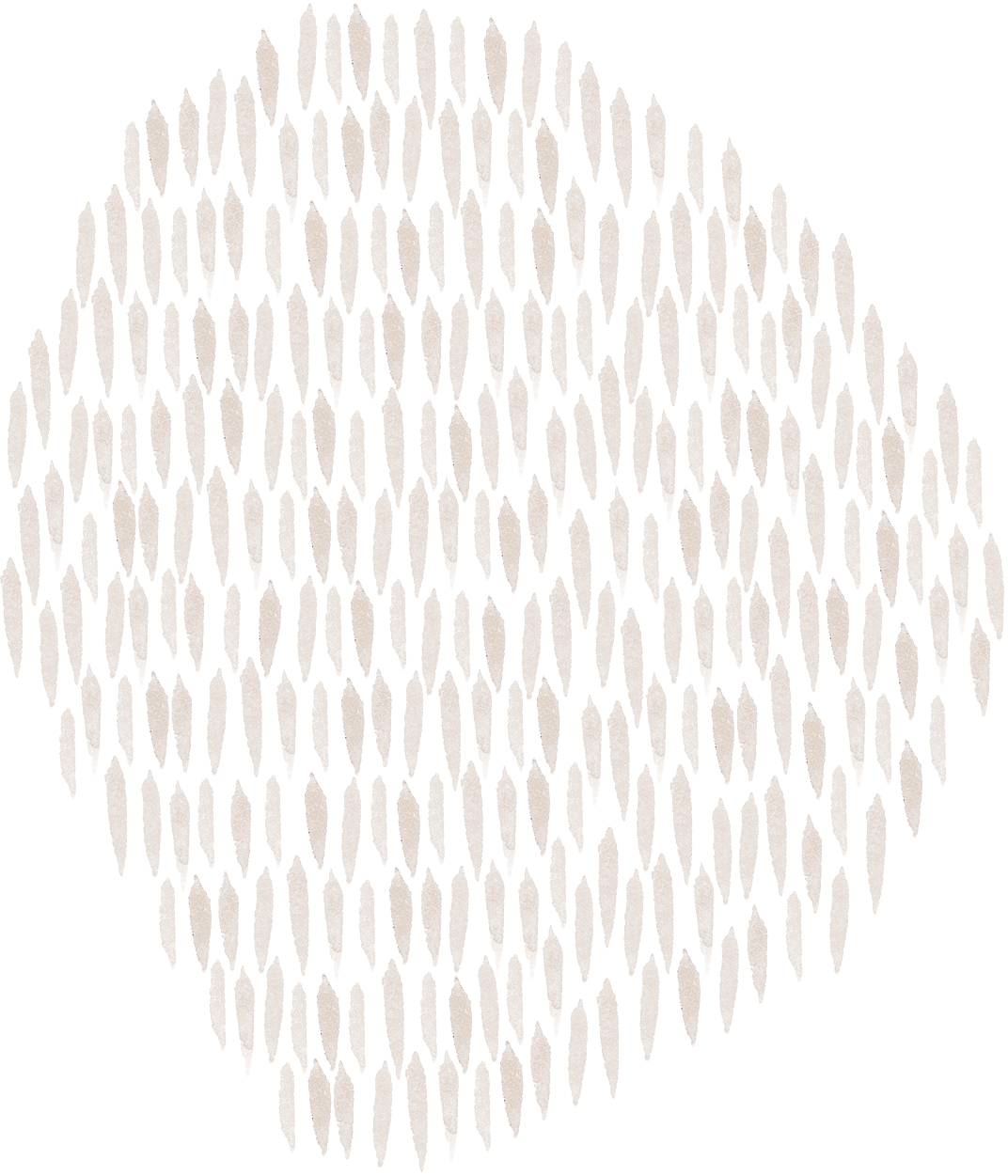平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
当社は誠に勝手ながら下記の期間を夏季休業とさせて頂きます。
8月10日(土)-8月15日(木)
尚、休業中にいただいたお問合せ等の返信は16日(金)以降順次対応させていただきますので何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます




いよいよ梅雨が明けて一気に猛暑になりましたねι(´Д`υ)アツィー
さすがにエステートハウスのモデルハウスに置きっぱなしの観葉植物たちが心配になったので引き上げてきて、さらにだいぶ購入時に比べて葉が増えて成長してきたので一回り大きい鉢に植え替えをしました。

ポットはamazonで、土と底のネットはダイソーで調達しました✌
ところがびっくりしたのがパキラの根。

土の上に見えている葉っぱに対して根がたったこれだけΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
しかも買ったポットに鉢底ネットを入れたら幹が半分でちゃいました( ̄▽ ̄;)

しばらく空調の効いた部屋で様子を見て、大丈夫そうならまたモデルハウス案内時に出動します!
パキラは手入れが簡単でどんどん葉が出るのでお部屋のグリーンに楽ちんでいいですよ!!
では今週もブログスタート
**********************************************************
前回投稿からだいぶ時間が経ちましたが芝生プロジェクトの続報です。
まずは当社事務所前庭二ヶ月前の様子がこれ↓

 こちらの今朝の様子がこちら
こちらの今朝の様子がこちら


暑い日には水やりをして、2回ぐらい施肥もしたらもうこんな感じです(*´Д`)
これをバリカンでガーっと買って、際をハサミでチョキチョキすること約20分


まだ生えそろっていない部分もありますがだいぶ芝の密度が上がり”マット感”が出てきました。
そしてこの”エッジ処理”

芝好きはこのエッジを見ながら白飯三杯は行けます( *´艸`)
やっぱり地球沸騰化時代の庭には芝生いいですね!
自宅の芝生についてはまた次回レポートしたいと思いますのでお楽しみに。
今週は物件の案内であちこち飛び回りながらの合間に投稿皆勤賞が途切れないようにがんばっています!というお話でした。




以前休日は野尻湖に通ってますよという話をしましたが7月からは群馬に戻り、榛名湖に通っています。

標高1000m級の山上湖は下界より7℃くらい気温が低く、蚊もいないので夏は榛名湖に限ります(*´Д`)
というかもう夏は暑すぎて榛名湖以外はムリ。

おかげさまでたまには良いサカナが釣れたりして、老後の楽しみにセルフ写真を撮り貯めています( *´艸`)
写真のフェイスマスクはここ数年何種類も試してようやく気温が低い時に偏光グラスが曇らないモノにたどり着きました。
結局穴が開いてるだけじゃだめでスリットですね。
では今週もブログスタート
***********************************************************
2023年3月17日、日刊工業新聞 にこんな記事がありました
「シリコンバレー超える」…群馬県と高崎市が飛行場跡地で描く最先端企業誘致の構想
記事によれば
街づくりは①先端情報技術を持つ企業などの集積②DXの活用③再生可能エネルギーを活用したサステナビリティの三つを柱とする。世界的な人工知能(AI)・IT企業や教育・研究機関を誘致し、DXを活用してMaaS(乗り物のサービス化)やロボット配送を実現。エネルギーの需給管理システムを導入する。
だそう。
さらに先月には日本経済新聞にこんな記事も
群馬・高崎、「シリコンバレーを超える街」は大言壮語か
おちょいちょいちょい。
建築と不動産を生業とする当社としてはいずれも突っ込みどころ満載です。
名だたる最先端企業や教育・研究機関を誘致したとてそこで働く人達の住環境はどうなんですか?と。
当然日本人だけでなく、それこそ世界最先端となれば外国人の方がメインとなるでしょう。
外国人となると日本人と違い勤める会社に対する忠誠心は薄く、自由が大好き、環境が合わない、奥様がNo!と言えばすぐにいなくなります。
なので群馬/高崎でシリコンバレーを超えると言うならまずは最先端企業に勤める「彼等/彼女等」とその家族が快適と思える環境を整備することが企業を受入れる前に先に整備すべき最重要課題なのです。
そこで私が思うシリコンバレー人材が集う街(仮称)群馬ITタウンに必要なお店をリストアップしてみました。
の第2弾、続きです。
先週はまずは完全に個人的な趣味でBass Pro Shops、そしてレストランがメインでしたが今週もやはり飲食系。
実際に住むとなるとやはり食べ物が合わないと。
ということで引き続きすでに日本に進出していて、群馬にも誘致できそうなところを狙ってみました。
ステーキハウスはとりあえずアウトバックにしておきましょう

私もアメリカに本格的に住む前に出張で使っていたホテルの通り向かいがアウトバックでお世話になりました。
まずあのオニオンフライにびっくりしますよね(@_@)
ここでは固めの赤みをミディアムレアでいただきましょう。
次はメキシカン。
個人的にはTEXMEXで良いのですが、あまりお店が思いつかないので近いところで深谷のアウトレットにあるあそこで。

あとは押さえでTACO BELLあたりでしょうか

そして欠かせないのがピザバフェ!

「All you can eat!」群馬らしく気取らなくて腹いっぱい食べられるCicCis PIZZAが欲しいです(多分まだ日本にないかも)。
Lake Forkに釣りに行く前にGarlandのBPSに寄って、このCiCis PIZZAで腹ごしらえしていざハイウェイ!がテキサスの週末の日課でした。
さらに当時会社の連中に「今日のランチはピザ奢るからCicCis集合な」と言って別れたらそれぞれが勝手に行きつけのCicCis PIZZAに行って、いくら待っても誰も来なかったというくらいDallasではそこら中にあった印象です。
あとは夜な夜な仲間が集まってひたすらダベることが出来るバーが欲しいです。
さすがにストリップバーは県の事業としては風紀上問題があると思うので日本ではレトロファッションと思われがちなプールバーがあるといいなと。
プールバーが難しいならスポーツバーでもいいや。
スポーツバーも思いつかないからもう日本にすでに出店しているところでハードロックカフェで!

そういえばTGIFも日本にあった!

とりあえずこれくらいの店揃えでスタートして、お店でワイワイしながら「次はあの店だ!」と盛り上がりたいです(妄想爆走中)
人が増えれば自然に地場のお店でも英語メニューが増え、英語での接客も当たり前になり、
学校ではクラスに数人の外国人の友達が出来て、
群馬から
「こんなとこでちっさくまとまってる場合じゃねーぞ!」
「オレもアメリカ生きてぇ!」
「本場のシリコンバレーで勝負してぇ!」
という血気盛んな若者が大勢出てきてグローバルに世界の中心で活躍して欲しいものです。
今週は食べ物のお店のことばっかり書いてたらもうお昼、腹減ったなーというお話でした。
引き続き日本のシリコンバレーにはこんな店、こんなサービスが必要だろーというアイデア募集しています!




昨日私ごとですが、毎年この時期恒例の(年次データ比較のため同時期にしています)健康診断に行って、これまた恒例のミニコント「おじさん健康診断あるある」を披露してきました。
【視力検査にて】
看護師さん:「はいじゃここを覗いて輪っかの切れている方向がわかったらレバーを倒してくださいねー」
私:「カチャ、カチャ、カチャ、*********、カチャ」
看護師さん:「うわー、両方とも1.5です!すごいですねー、羨ましい♡じゃ次は採決になりますねー」
【採血にて】
看護師さん:「はい、こちらでお名前お間違いないですかー?(採決容器を差し出す)」
私:「近すぎて見えません。。。。」
(*´Д`)
私は子供の頃からずっと視力だけ( *´艸`)は良く自慢だったのですが、年齢を重ねるにつれ日常生活でも不便なことが多くなり、まいったなーと思っていました(一番困るのはまだ薄暗い時間に釣りでハリに糸を通す時)。
ところが中国語では「老眼」を「花眼(ホワイェン)」と言い、花は細かいところ見るものではなく、全体を見て味わうものなので、それができるようにな歳になった。→いい歳になったら細かいとこなんか見えなくていい→なんなら見ない方がいいという考え方があるという話(もはや出典を覚えていませんが)を聞いて一気に「老眼」がポジティブなものに。
それまでは見えないモノを見ようとして(?バンプ?)無理していたことが「ああこれは見えなくていいんだ、ってか私が見る必要はないんだ。見える人に任せればいい♡」と必死に下を向いていた顔を上げて周りを見渡すと逆に今まで目に見えていたものの違った良さや見え方が発見できるようになりました。
今視力が良いと自慢のあなた!
早ければ30代から来ますよ老眼!
でもそれは「花眼」と思えば小さいことはひとに任せて早期出世しろってことかも( *´艸`)
何事もポジティブ、ポジティブ
では今週もブログスタート
***********************************************************
2023年3月17日、日刊工業新聞 にこんな記事がありました
「シリコンバレー超える」…群馬県と高崎市が飛行場跡地で描く最先端企業誘致の構想
記事によれば
街づくりは①先端情報技術を持つ企業などの集積②DXの活用③再生可能エネルギーを活用したサステナビリティの三つを柱とする。世界的な人工知能(AI)・IT企業や教育・研究機関を誘致し、DXを活用してMaaS(乗り物のサービス化)やロボット配送を実現。エネルギーの需給管理システムを導入する。
だそう。
さらに先月には日本経済新聞にこんな記事も
群馬・高崎、「シリコンバレーを超える街」は大言壮語か
おちょいちょいちょい。
建築と不動産を生業とする当社としてはいずれも突っ込みどころ満載です。
名だたる最先端企業や教育・研究機関を誘致したとてそこで働く人達の住環境はどうなんですか?と。
当然日本人だけでなく、それこそ世界最先端となれば外国人の方がメインとなるでしょう。
外国人となると日本人と違い勤める会社に対する忠誠心は薄く、自由が大好き、環境が合わない、奥様がNo!と言えばすぐにいなくなります。
なので群馬/高崎でシリコンバレーを超えると言うならまずは最先端企業に勤める「彼等/彼女等」とその家族が快適と思える環境を整備することが企業を受入れる前に先に整備すべき最重要課題なのです。
そこで私が思うシリコンバレー人材が集う街(仮称)群馬ITタウンに必要なお店をリストアップしてみました。
「彼等/彼女等」は仕事では効率を求め、人付き合いは比較的カジュアルを好み、オフには家族でアウトドアも積極的に楽しむという前提で
まずはなんといっても
Bass Pro Shops:https://www.basspro.com/shop/en#

随分前から日本にバス・プロ・ショップスを誘致したい、老後はそので入口で「ハロー」と手を振るおじさんになりたいと公言していた私としては遂にその時が来たなと。
アメリカで言えばCOSTCO→IKEAときたらBPSでしょ!となる訳です。
そしてネーミングライツでBPSまでの道は「バスプロドライブ」と名付けられ、道案内でも「突き当りのバスプロドライブを東へ」と。
もう赤城山や榛名山が群馬県民の方角の目印じゃな無くなる訳ですよ!
ここでお店づくりや品ぞろえのスケールの大きさを日本の人達も肌で感じ、このスケール感が当たり前で生活した来た人達と共に仕事をすることで世界に通じる人材が育つわけです!
次にHOOTERS:https://www.hooters.com/

「彼等/彼女等」は常に新しい刺激、新しい仕事、キャリアアップを目指しています。
そんな「彼等/彼女等」の社交場、情報交換の場としてカジュアルバー、スポーツバーが欲しいところですがここはすでに日本にも出店しているフーターズで手を打ちましょう。
そして仕事に効率を求める「彼等/彼女等」もやる時は徹夜でもやります。
そんな時に超便利なのがPANDA EXPRESS:https://www.pandaexpress.com/
 私もアメリカ在住時はほんとにお世話になりました。
私もアメリカ在住時はほんとにお世話になりました。
オレンジチキンとブロッコリービーフとチャオメンが私の定番で、最終的には店に入っただけでいつもの彼女が勝手に盛り付けて「Right?」と笑顔でプレートを渡してくれるようになります(PANDEXあるある)。
よくアメリカの映画でもFBIやCIAが張り込み操作をしたりするときにクルマの中や本部指令室で小さなボックスにパンダの絵が書いてあって不器用に箸を使って食べてるアレです(*´Д`)
こちらもすでに日本に出店しているので間違いないでしょう。
そして忘れてならないのはインド系レストラン。
世界中どこへ行ってもIT技術者はインド系が多いので彼らの食欲を満たすレストランがあるのはマストです。
インドカレーのお店はすでにいくつかあるのでここはカジュアルにバフェスタイルのお店がひとつ欲しいです。
 :https://indiapalacedallas.com/
:https://indiapalacedallas.com/
ここは私がダラスでヘビロテリストに入っていたお店ですがだいたいこんな感じで。
いやーまだまだ必要ですね、ですが後が長くなるので今週はここまで。
今週は県の事業に乗っかって自分の理想の街づくりを虎視眈々と狙って妄想リストを作成中というお話でした。
海外経験豊富な方で「いやこれ絶対必要でしょ」というお店や施設があればぜひメッセージお待ちしています。
一緒に(仮称)群馬ITタウン妄想リストを作り上げましょう!




このブログをいつも読んでいただいている方は「最近シクラメンの話しないね、さては無かったことにしようとしてるな。。(。-`ω-)」と思われていたかもしれませんが芝管理と並行して今年もシクラメンの夏越しチャレンジも継続しています。

これ、山菜ではありません( *´艸`)
次々と葉が枯れて行く中で新しく出てきた葉が開く手前で生育が止まってしまいこのような状態になっています。
現在は直射日光の当たらない空調の効く室内に鉢を移動していますのでこのまま葉が開けば継続して水やり(非休眠法)、完全に枯れてしまえば水やりもストップして休眠させます。
ただこれまでと違うのが球根の頭がでかい(@_@)!

今までは秋に掘り返してもカラッカラになった根っこしか無いような状態でしたが今年は🤩
おそらくこのまま休眠法に入ると思うので秋に掘り出すのが楽しみです。
では今週もブログスタート
**********************************************************
いよいよ新紙幣の発行が来週3日にせまりニュースでもあらためて取り上げられる機会が増えたように感じます。
インタビューではラーメン店の店主が「券売機を新紙幣対応に改造するのに○○万もかかるので、らーめんも値上げせざるを得ないです」とも。
そうなんですよね、新札が発行されるということはそれに係る全ての機器を更新しなければならないので景気を刺激する効果を持つ反面、余計なコストや時間がかかることで生産性が低下する、先ほどのラーメン店の話のように結果値上がりに影響するなどさまざまな影響があります。
”政府広報オンライン”
ところで皆さん不思議に思うことがありますよね、新札発行前にどうやって新札対応の券売機(もっと正確に言うと「紙幣識別機」の部分)を作っているんだろう??と。
実は私が以前勤めていた会社はこの紙幣識別機(「ビルバリ」「ビルバリデータ」とも呼ばれ社内では”ビルバリ”で通っていました。ちなみに硬化識別機は「コインチェンジャーメカニズム」、社内では”コインメック”と呼ばれていました)を作っていて、私も多少関わっていましたので今回の新札発行のニュースを聞いた時に「あーメーカーは大変な思いしてるんだろうなー」と思いながら見ていました。


写真はウィキペディアに掲載の
1866年→ まだサムライ
1867年→ チャップリン風紳士
というたった1年でのビフォーアフターにびっくりしたのでご紹介
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
さて、新札を識別するには当然新札が必要になります。
ここからは20年以上前の話なのであくまで参考か都市伝説的な感じで読んでください。
なのでまずは日銀だか印刷局に行って身分証明というか事前に新札を取扱う人を登録します。
これって優秀なプログラマーがハッカーにもなれると同じで、紙幣識別装置が作れるということはそれをだます偽札も作れる技術を開発する可能性もあるので、開発に関わる彼等は「容疑者リストに登録された」と言ってました。
識別装置の製造エリアとそこで働く人は厳重に管理され、当然ですがお店のレジのように仕事終わりに検査用紙幣の残高が確認できるまで帰れません。
※たまになかなか数字が合わなくて、どうしても用事があるのでしょうがないから自分の財布からお札を出して帰った人がいた!?という噂も。。
紙幣の場合何が大変かというと新札(いわゆる”ピン札”)と使い込んだヨレヨレのお札や一部か切れたり、欠けたりしたお札もホンモノであれば使えるようにしなければならないところ。
本体にセンサ(←マイクロソフト式だと「センサー」)の感度を調節するボリュームがあり、それをドライバーのような工具で感度調整する訳です。
偽札を絶対通さないぞ!と思えば感度をMAXにすればよいのですがそうすると財布から取り出したヨレヨレのお札が使えない(あれってイライラしますよね!)となります。
じゃあ感度を緩くして。。。としちゃうとお粗末な偽札まで通してしまうというジレンマ。
当然偽札判定が多くなると1台あたりの検査時間にも影響して生産性も悪くなり深夜まで残業となってしまいます(懐かしい(*´Д`))。
このへんの感度設定とそもそもの検出技術(プリズムだったり磁気だったり、それらの組合せだったり)が各メーカーのノウハウとなる訳です。
もちろん検査のためとは言え偽札は絶対に作っちゃダメ!!ですから。
当然、偽札被害が少ないと評判になる→じゃあウチもお宅のメーカーでとなります。
が、偽札被害が少ない=偽札検出能力に長けていると思うのは消費者だけで、警察など犯罪を取り締まる立場では偽札検出能力に長けている=他社製品をだます偽札製造ノウハウがあるとみなす訳です。
なので当時の製品の性能が良かったらしく開発担当者が某警察に呼ばれて「なんでお宅の製品は偽札通さないの?」と任意の事情聴取?と思われるプレゼンの機会を与えられたと話していました。
結論としては当社だけが他社と異なる検出方式を使っているのでということを説明して釈放?になったと言うことでした。
余談ですが「ニセ500円硬貨」事件が流行っていたころに”コインメック”製造にも関わっていたのですが当時採用された画期的技術が”エスクロ機能”
”株式会社オクト様のwebサイト”より
ようするにこの機能が採用される以前は自動販売機や券売機が偽硬化、偽札の両替機になってしまっていたんですね。
これ、作る側からするとまた大問題で、これまで硬化を投入して吐き出すだけで良かった試験がエスクロ機能によりいったん偽コインをアクセプタ(詳しくは上記URLを参照)に保留するため1台当たりの検査時間が恐ろしく伸びてしまうのです(→また徹夜の刑)。
新札、新硬化が出るたびにメーカーは特需で盛り上がるのでしょうがインバウンド需要の増加、ユニバーサルデザイン化、犯罪防止(治安が悪い国は外に自販機なんてありません。だから外国人観光客が珍しくて販売機の写真撮るのです)、集金担当者の肉体的負担(硬化は大量になると重いのでルート台数が多いと腰痛になると聞き増した)などを考えるとICやQR決済化の流れが主流になるのでしょうね。
昭和生まれの私でさえ最近は小銭持ち歩かないですし、店に入る時は現金以外使えるかな?と確認しますもん。
それはそれで決済利用手数料をお店が負担するので経営を圧迫することになるかもしれませんがCMのように「じゃぁいいでーす」と言われるよりマシか┐(´∀`)┌
今週は新札発行と聞くとそれにまつわるいろんな人達が苦労したり、儲けたり、泣いたりしてるんだろうなと思うところがありますというお話でした。
個人的には「渋沢栄一アンドロイド」が絶妙にはまって気になっています!
渋沢栄一デジタルミュージアム
https://www.city.fukaya.saitama.jp/shibusawa_eiichi/1592454024442.html
写真は渋沢栄一デジタルミュージアムHPより
※講義を受けるには要予約です!




いよいよ関東地方も史上最遅れの梅雨入りになりそう(なった?)ですね。
水資源のことを考えると降るべき季節に降るべき適量が降ってくれるのが一番ですが例年と同じ量の雨が短期間に集中して降られたら「想定外」。
梅雨明けまでは毎日の天気予報と高湿度による室内熱中症にも中止ながら過ごしましょう。
先ほど急遽新規のお客様のご予約が入ったので今回小話は短めに(*´Д`)
今週もブログスタート
**********************************************************
4月に開設された物件探しの参考になる不動産の取引価格や学区、ハザードマップなどのデータをウェブ上の地図に重ねて表示できる国土交通省の「不動産情報ライブラリ」がこれから家や土地を買おうという界隈では大バズリしているそう。
開設2ヶ月で500万アクセスってすごいですね。
サイトURLはコチラ↓
不動産情報ライブラリ?いや待てよ、そんなんウチはとっくの昔から「高崎不動産情報ライブラリー」っていう情報発信サイトを運営してますやん!
我らが「高崎不動産情報ライブラリー」はコチラ↓
今回の「不動産情報ライブラリ」の開設にあたり国交省からは特に連絡もありませんでした。
余談ですが「ライブラリー」と「ライブラリ」はマイクロソフト規格とJIS規格による違いです(多分)
当社は日本の枠を飛び越えて活躍するためにグローバル企業のポリシーに賛同して「ライブラリー」を採用しました!!
以下参考に、ちょっと人に話したくなる豆知識になるかもしれませんよ
私こう見えても(見えてないか)大学時代は工学部で、化学専攻でしたが当時機械工学専攻だった友人Fが「JIS規格でカタカナの最後は棒「ー」をつけないことになってるから「モーター」が「モートル」なんだよ。」と偉そうにウンチクを語られました。
さらにそのFは「だからオレはJIS規格に準拠して食堂でカレーを頼む時も伸ばさずに「カレ」っていうんだぜ」とのたまう始末。
(上のサイトによれば「カレー」は2音なので「カレー」のままで良かったのでは。。。。)
今はFと付き合いがありませんが、どうかあちこちでいざこざを起こさず、穏便に幸せに過ごしていて欲しいものです。
さて、皆さんの期待通りに話がそれましたがこの「不動産情報ライブラリ」すごく便利です。
トップページはこんな感じで自分の調べたい地域を選んでメニューを進めます。

アンケートがあるのでどうやらこのアンケートを基に不動産取引価格をアップデートするのでしょうか。
アクセスすると調査票が届くかもしれません。
地域を選ぶとタブのメニューで自分が知りたい情報が選べます。

私がここでよく言う「市街化区域」「市街化調整区域」もここで「都市計画情報」をクリックすると選択できます

素晴らしいですね。
自分で何でも調べたい派の方には持ってこいのツールだと思います。
不動産屋さんに行ってその後の営業電話がしつこいとか嫌ですもんね。
このサイトを使ってご自身の納得が行くまで検討されるのも良いかと思います。
今までこれらの情報を提供するのが一番の仕事だったという不動産営業マンは失業しちゃうかも( ̄▽ ̄;)
が、実はもっと簡単な方法がありまして、当社の「物件提案ロボ」というAIがお客様の希望する条件にあった不動産情報を提供するというサービスに登録しちゃうことです( *´艸`)
※どちらも1回登録すれば両方のサービスが使えます。
マンション/戸建をお探しの方↓
物件提案ロボ:https://self-in.net/era/rlp/index.php?id=takasaki01
新築用の土地をお探しの方
土地情報ロボ:https://self-in.net/era/llp/index.php?id=takasaki01
これらに希望条件を登録しておけばAIが最新の情報を毎日メールで届けてくれて、気になる物件が見つかった時だけ「問合せ」ボタンをポチっと押せば私達が「不動産情報ライブラリ」以上に詳しい「物件レポート」を無料でお届けしますのでさらにお客様の手間が省けます✌
今の時代最も価値があるのは時間と情報です。
便利なツールを使って必要な情報を必要な時に手に入れることで時間を有意義に使われることを強くおススメします。
今週は国交省のサイトの紹介と思いきや最終的には自社サービスの営業かーいというお話でしたが
新聞で「不動産情報ライブラリ」大バズリというニュースを読んで、こっちの「物件提案ロボ+物件レポート」の方がホントにお得な情報なので書かずにいられませんでした。




当社は電気使用量、ガソリン使用量、コピー用紙使用量を指標に年々成果を上げて今年も認定されました。
特に不動産では未だに現役のFAXをスマホで見られるようにクラウドデータ化したのはコピー用紙削減に寄与しただけでなく、「事務所に戻って確認しますね」が無くなって生産性も上がりました。
おススメです♪




今週は”5年ぶりの運転免許更新(=ゴールド免許)”に旧パスポートセンターに行ってきました。
前回更新はコロナ前なので更新の手続きもいくぶんシステマチックに変わり、対人距離も適度に保たれて、大変ではあったけどコロナ禍が世の中のいろいろな仕組みを見直すきっかけになったことは間違いないと改めて感じました。
更新申請書は免許証を機械に差し込むと自動で作製され、自分で書くのは電話番号と質問の✓だけ。
あとは前回も何にいつ使うんだろ?という暗証番号もタッチパネルで入力するとレシートみたいに印字されて出てきます。
※免許証と一緒に保管しとけば無くさないと思ったら「免許証と一緒に保管しないでください」と書かれていました。。。(*´Д`)
そして窓口で更新料を支払うのですが今回も交通安全協会会費、払ってしまいました。
毎回これってNoって言えるんかな?確か更新案内のハガキが来るか来ないかだけの違いじゃなかったっけ?
と思ういながらも窓口に行くと「安全協会に加入していただけますか?」というほぼ強制に近い笑顔に
お人好しの私は「いいえ」と言えず、恐らく私が身の回りで唯一あまり使途や費用対効果にこだわらず払う費用だと思います。
もはや募金に近い感覚でしょうか。
良くネットやテレビで見る家計相談でもこれまで「交通安全協会会費削減で年間500円の効果!」と言ったファイナンシャルプランナーは見たことがありませんものね(*´Д`)
会計報告書を見たことはありませんがドライバーの皆さんの大切なお金が有効に使われることを願っています。
それからは人間ドッグと同じように案内テープを辿っていくと適性検査→ 申請 → 写真撮影 → 安全講習 → 免許交付と進んで行きます。
途中までは番号なのに最後の交付だけはこれだけ個人情報にうるさい世の中なのに未だにフルネームが呼ばれるのには違和感がありました。
5人ぐらいのロットで処理する姿を見て、やっぱり決まった数で処理するって効率がいいんだろうなと先日のブログで書いたラーメン屋さんを思い出しました( *´艸`)
そして受け取った新しい免許証と穴の開いた免許証の写真を見比べて「ああまた歳をとったなぁ」と実感したのでした。
では今週もブログスタート
*******************************************************
最近は留学経験のある方も増え、もしかしたらこの円安を利用して来日を計画しているご友人がいらっしゃるかもしれませんね。
そこで「じゃ今度日本に行ったらレンタカーを借りて自分で運転もしてみようか!」と意気揚々と国際免許を取得してくる外国のご友人がいたらぜひ今日の「※国際運転免許証の3ヶ月ルール」は覚えておいてください。
※運転免許証の有効期間内でも日本で運転できなかったりします!!
これは私の友人が実際に経験したことなのですがたまたま警察に運転免許証の提示を求められた際にこの「3ヶ月ルール」に抵触するのではないかと、真偽が明らかになるまで某警察署の一室にとどまることになってしまったのです。
連絡を受けて私が警察署に行くと「どういったご関係ですか?」から始まりなかなか会わせてもらえません。
ですが署内には英語が話せる人がいないらしくあたふたしている様子はうかがえます。
結局私ちょっと英語話せますというと面会が許され、なぜ彼がここにいるのかを説明するのに私も初めて「3ヶ月ルール」を知りました。
群馬県では滅多にこんなことはないのでしょう。
警察署の人も初めて「3ヶ月ルール」を取扱うようで、そもそも何のためになぜそんなルールがあるのか、必要なのか、私が日本語で聞いてもその場では”とにかく”と言うだけで誰も理由は説明できませんでした。
そして警察の中の通訳?みたいな人が来て事情聴取して、パスポートの記録を確認するまではここに居てもらいますと。
さらに「もし詳細に調べた結果3ヶ月ルールに抵触していると無免許運転となりますのでご友人のクルマを宿泊先まで運んでもらえますか?」と。
「じゃ本人はどうやって帰るんですか?」と聞いたら「我々が送り届けます」と。
んーなんだかわかったようなわからないような。。。
ただ私も仕事の途中だったので一旦戻って運転代行要員を確保した上で再度警察署へ出向き友人のクルマを運転して届けました。
後に友人にメッセージを送ると「at home」と、とりあえず釈放?無罪放免?
聞けば特に切符も切られず、罰金もなく、治外法権的な扱いだったよう。
そしてしばらく日本にいるなら”日本で有効な免許証”を早く取得してくださいと言われたそうです。
出典:警察用HPより「外国の運転免許をお持ちの方」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
私もこの3ヶ月ルール、警察の方の説明を聞いてもよくわからなかったので調べました。
出典:警察庁HPより「国際運転免許証で運転できる期間」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/HP3monthpicture.pdf
結果日本と米国を行ったり来たりしていたので、おそらく資料の”(2) 外国滞在3月未満で再び上陸した場合(外国籍の方に多いケース)” に該当したのかも知れませんがこれを見て普通に理解して説明できる人います??

同じように日本国籍の人も3ヶ月ルールがあるので気をつけた方が良さそうです。

私も海外出張が多かった頃は国際免許で運転したこともありましたが「どこでも1年間有効ですよー」と言われ、レンタカーを断られたこともありませんでしたので私の場合は大丈夫だったのでしょうね。
何故?何のために?と深堀するとネットではいろいろ書かれていますがどれも腑に落ちず謎のルールです。
が、ルールはルールなのでもしこれからお友達が日本に遊びに来るのを計画しているよーとか、逆に海外に行ってくるよーという方、割と頻繁に海外に行き来する方は念のため”国際免許証で運転できる期間”を事前に確認して、万が一にもトラブルが無いように気をつけましょう。
ちなみに警察の方がポロっと言ってたのが「日本だけらしいんですよねぇ、こんなややこしいの。。」と、おそらくそうでしょうね、他の国ではこんなに難解なルール絶対にあり得ないでしょうね。
今週は決して体制批判ではなくて、インバウンドで盛り上がる一方で我々もいろんなルールがあることを知っておかないとせっかくの楽しい来日がしょんぼりする結果になってしまいますよというお話でした。
でも今回は友人が事故を起こした、事故に巻き込まれたという話ではなくホッとしました( ̄▽ ̄;)




このところ不動産の売買や新築のご相談で外国籍のお客様が続いています。
英語はアメリカに5年住んでいたのである程度のコミュニケーションは取れるのですが日本語でも普段は使わない法律用語や契約に関する専門用語などはスマホの翻訳機能が頼りです。
保険の契約などの場合はさらに病名など難しくなりますがこちらは逆にお客様がスマホをかざして即翻訳されて、「大丈夫です」と(*´Д`)
中国語になると旅行に必要な最低限の単語が分かる程度;つД`)
頻繁に出張で出かけていたのが2003年~2005年くらいで、当時は海外出張のたびにダイソーのCDで学ぶ会話シリーズを買って、せめて空港からホテルまでとメシを食べてチェックインぐらいは現地の言葉で出来るようにと勉強(?)していました。
仕事場に行けばどこの国へ行ってもほぼそれぞれの国の御国なまりの英語でコミュニケーションをとるのでさほど不安はありませんでした。
で、当時の上海で好評だったのがこのダイソーの学ぶ会話シリーズの本。
誰に好評かというとカラオケ(歌うわけではなく当時は夜の社交場として日系企業の皆さんが集まる場所でした)のお店で働く小姐さん。
彼女たちはまず日本語のデュエット曲で日本語を覚えて、それから徐々に会話というパターンらしいのですがその両方が書かれている会話シリーズの本は彼女達からすると日本語の勉強に最適だと。

なので次の出張の際には「やさしい日常中国語会話」を10冊ぐらい買い込んで行き、私はそれを実際に発音してもらうことで中国語を勉強しました( *´艸`)
その他にもアメリカ滞在時はメキシコもちょこちょこ出張で行ったり、職場にもメキシカンが多かったのでスペイン語も挨拶程度は勉強して、ただドイツ語、フランス語は行く機会が少なかったで勉強しようとダイソーで本を買ったけど全然ダメでした。
そんな訳で、外国語を学ぶのには各言語100円+税しか投資せず、あとは現地の人とひたすら喋って耳でなんとなく覚えるといういい加減なコミュニケーション能力を身に着けたおかげでここ最近の顧客グローバル化になんとか対応しています。
それでも自分が海外へ行った時に自国の言語で話しかけられたら一気に距離が詰まるので(ただそれが現地詐欺の手口でもあるので要注意ですが)アイスブレイクとして、また「これはあなたの国の言葉でなんて言うの?」とか聞くと自然と会話が弾んでお互いの緊張感もほぐれます。
私自身のコミュニケーション能力はともかく、今来られているお客様のように、観光目的ではなく本気で群馬に住みたい外国人の方がもっと増えるいいなと思っています。
それによって地域の人達や学校、自治体もグローバルコミュニケーションに慣れて、そこで育った子供達は海外コンプレックスを持つことなく(私の育った時代と違いすでにないのか??)世界で活躍できる人材になるのではと期待するからです。
今風に言えばグローカル?化ですね!
ウィキペディア「グローカル」
”https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E5%8C%96”
今週は久々に外国籍のお客様と触れ合って久々に英語脳と中国語脳を呼び起こして脳が活性化されたと勝手に思っていますというお話でした。
では今日はこれから米国籍2組、中国籍1組、午後から日本国籍1組の商談に行ってまいります!




先日のこと、毎月恒例の現場巡視の途中に気になっていたラーメン屋さんに寄ってみました。

そこは偶然ドライブ中にウチの下の子が「あっテレビに出てたラーメン屋さんだ!」と見つけたところで、GWに行ってみるかとなったのですが休みだったのでそのまま行こうぜという話は自然消滅していました。
それがちょうど通りかかったのが11時頃で、「確か店のオープンが11時だったな、今なら並ばずに入れるか!?」と突撃してみたのです。
”食べログ”
https://tabelog.com/gunma/A1001/A100101/10023603/
するともう店は開いていたのですが入口の前には行列が出来ていて、食券の買い方もわからない初心者は常連さんと思われるお客さんの間で緊張感が走ります(;´Д`)
とありあえず店内の貼紙でいちばん大きく書かれていた「まぜそば」の並みを食券で購入(コッコマンて何だ??)。
呼ばれるまで座って待つ仕組みです(※二郎系のコールはこれまた常連さんの前だと緊張します)。
さてイスに座ると目の前のカウンターにはなんと小学生の男の子たちが7人ならんで座っています(@_@)
端から店員さんにトッピングを聞かれるとみんな顔を見合わせてどうする??とうする??と
そこで7人の中ではふた回りぐらい体格の大きい真ん中に座っていた子が「オレはいつも○○○だから」みたいな助言を
すると「じゃオレも」「オレも」。。。と端まで行ってひと段落(*´Д`)
彼等は緊張気味に、すごく姿勢正しくカウンターをのぞきこんで待っています。
カウンター下に置いてある道具を見ると野球チームの仲間なのでしょうか、
平日なので恐らく運動会の振り替え休日に
「例の大盛りのらーめん、食いきれるかみんなで試しに行くか!? オレは行ったことあるからついて来いよ!!」
と漢気を試すイベントを企画したのでしょう、大柄な彼がリーダーとして、7人の真ん中に座って面倒を見ている感が伝わってきます( *´艸`)
私も隣で座って待っている常連さんらしき人にいろいろと尋ねて「いつも何をオーダーするんですか?」「おススメのトッピングは?」とか「課長って何なんですかね?」とコミュニケーションを図って自分の緊張をほぐします。
そしていよいよらーめんが少年達の前に運ばれるとまたみんなが顔を見合わせて、声には出さずに「おおーこれか。。。」と。
そこからは彼等はこのらーめんに負けてなるものかと、絶対に完食してやるぜ!という意気込みで一心不乱にらーめんをすすります。
時々顔をあげて横目で仲間の食べっぷりを確認しながら。
いい食いっぷりだ、がんばれ!とおじさんも心で応援!!
やがて何人か食べ終わって満面の笑み。
後ろで待っているおじさん達に気を使って食べ終わった子から外へ出ます。
「ごちそうさまでした」と、うむ礼儀正しくてよし。
やがて真ん中に座った大柄な子とその両脇にひときわ小柄な子達が残ってしまいました。
「やべー、食えねーかもしれねー」「大丈夫だよ、オレがチャーシュー食ってやるよ」
「オレもやべー」「大丈夫だよ、野菜はオレが全部食ってやるよ」
自分は食べ終わった真ん中の大柄な子が両脇の子の面倒をみて、なんとか完食させようと頑張っています。
おおー、最初から小柄な子が食べきれない場合に面倒見るのを想定してこのフォーメーションで座ったとしたらこの大柄な子は相当できるな!とおじさんも感心することしきり。
席が空いても呼ばれないので隣の常連さんに訊ねたところ「ここは7人ロットでさばくみたいですよ」と。
つまりカウンター7席が全部空かないと次の7人が呼ばれないということ。
なるほど、少年よ、プレッシャーに負けるな!がんばれ!
そして残った子達もリーダー(もはや大柄な子をそう呼ぼう)の助けもあって完食(/・ω・)/
「ごちそうさまでした!」と気持ちよくどんぶりをカウンターに(これもリーダーの指導による)戻し、
店員さんも「よく食ったな、また来いよ!」と。
(フレンドリーな店員さんで良かった、とおじさんも安心)
あー、なんかいいなー
彼らにとっては自分達の仲間だけで店に入って食券を買い、ここのらーめんを完食するっていうちょっとした冒険だったんだろうなー
面倒見のいいリーダーはきっと学校でも学級委員で、もしかしたら行く行くは生徒会長かもしれないなー
いやいや面倒見のいい区長さんから市議会議員か市長も狙えるなー
死体探しはしてないけどなんか映画のスタンドバイミーみたいな少年時代の思い出になるんだろうなー
歳を取って、同窓会で久々にあって「あんときお前のチャーシューオレが食ってやったんだぜぇ」なんて話すんだろうなー
と、勝手にほっこりとしてしまいました。
「スタンド・バイ・ミー」→ ”ウィキペディアより”
そんな彼等を見送った後、自分を含む7人のロットがカウンターに呼ばれ、初心者の私は「あのー初めてなんですけど。。。」と店員さんにオーダーのレクチャーを受けて無事にトッピングをオーダー。
午後も仕事があるのでニンニクは少な目です✌

オーダーした「まぜそば」は並みにしといて良かった~という量で、それでも満腹中枢が刺激される前にと大急ぎでかき込んでなんとか完食。
その日は晩飯もいらないぐらいずっと満腹状態でした┐(´∀`)┌
今週は少年たちの冒険に刺激されたおじさんもがんばって完食したものの午後は腹がパンパンで苦しかったというお話でした。
でも頭の中では子供の頃の仲間との悪戯を思い出して映画スタンドバイミーの主題歌が♪ 少年達にいいもの見せてもらいました。




今週水曜日に前橋市富田町(上武国道から見えるパワーコメリのすぐ近く)にザスパクサツの練習場&クラブハウス”ザスパーク”が遂にオープン♪
https://thespa.co.jp/thespark/
コメリ目の前で新モデルハウスを建築中なので現場巡視がてら早速タニタカフェへ行ってランチをいただいてきました(*´Д`)

ランチ営業終了間際1:59に滑り込みセーフ(;´Д`)
ワンプレートは1日に必要な野菜量の1/2以上の量を楽しく、おいしく食べられる、タニタカフェオリジナルのデリプレートです。
メインは3品から選べます
A マスタードソースのチキンソテー~香ばしアーモンドパン粉~
B グリルハンバーグ~きのこデミグラスソース~
C サーモンのオーブン焼き~いぶりがっこマヨネーズ~主菜をチキン、ハンバーグ、サーモンから選べて私はチキンを選択♪
私はチキンもナッツも好きなので迷わずAを選択♪
味はもちろん美味しく、タニタカフェで食べたというだけで健康になった気がしました( *´艸`)
外のデッキに出ると広大なグランドがあってまだ天然芝は種まきしたばかりのようで絶賛水撒き中

芝生!?と言えば。。
最近芝生ネタを書いていなかったので今週は久しぶりに芝生の現況を報告したいと思います
では今週もブログスタート
**********************************************************
今現在私の芝生プロジェクトは3ヶ所
うち1ヶ所のモデルハウスはおかげさまでお客様にご購入いただきましたので今週最後の芝刈りをしてきました。


2年目なのでもうだいぶ密に生え揃っていますね。
手をかけた芝とのお別れはなんだか名残惜しい気もしますがお客様は早速BBQを楽しんだり、お子様は裸足で遊んで気持ちよさそうです。
これからお客様にはお引渡し後のお手入れのため私が使っていた電動芝刈り機を中古ですがプレゼントすることになっていますので芝ライフ楽しんで欲しいです!
2つ目は当社事務所前庭

 こちらは今年の3月に貼ったのでまだまばらです。
こちらは今年の3月に貼ったのでまだまばらです。
面積が狭いのでいわゆる”芝刈りバサミ”で行けるかなと思ったのですがやってみると手がパンパンになって(-_-;)
その後のPC業務に支障が出たことからハンディタイプの芝刈り機を導入しました

手押しタイプの芝刈り機には狭いけど手で刈るには広い。。。みたいな広さにちょうどいいです♪
3つ目は自宅の地球沸騰化対策リフォームした庭の芝

こちらは3月を待ちきれずに2月に貼った姫高麗。
まばらですが伸びたところはもうだいぶフサフサしてきたのでそろそろ刈ってみようかと思っています。
ここは先ほどのハンディバリカンには広く、電動芝刈り機には狭いので手押しの芝刈り機を導入予定です(芝好きの方はすぐにわかると思いますが例のアレです)
これから暑さが増して来てうわーってなりがちですがその中で青々と、そしてキリっと刈り込まれた芝生は「夏もいいな」と思わせてくれます。
今週はご自分の体力と時間と性分にあった広さの芝生ライフおすすめですよというお話でした。




今週は初めて子供達の企画でディズニーに招待され、10数年ぶり??に行ってきました。
先を歩く子供たちの後をついて歩きながら、「コーヒー飲みてーなー」というと財布を渡さなくても買ってくてくれるということに子供の成長をしみじみと感じたのでした。
来月オープンの新エリアのアトラクションにもなんとかチケットで入り「今はね、時間はお金で買うんだよ」としたり顔で語る娘にそうそう、それが世の中の仕組みなのさと心で相づち。

ネタバレにならないようにアトラクションの内容は書きませんが技術の進歩はすごいですね~、メガネかける系のアトラクションが苦手なおじさんはまだ脳が揺れてる感じがします(@_@)

写真はソアリンの待ち行列で見つけた地鎮祭と思われる絵。地縄が張られていますね。
来週は新モデルハウスの地鎮祭があるので思い出しそうです( *´艸`)
では今週もブログスタート
*****************************************************
私の趣味はというと魚釣り、特にここ10年来はバス釣りにはまっています。
バスにも種類があって、毎年GW明けのこの時期はスモールマウスバスを狙って長野県の野尻湖へ遠征しています。
関越と上信越道を使ってちょうど片道2時間くらいですが道中のドライブも楽しく、普段街乗りでストレスを感じているであろうクルマもご機嫌です(※と言いながら昨年はエンジントラブルでレッカー帰宅を経験(;´Д`))。

釣れたらもちろん楽し
釣れない時も野尻の風景はとても癒されます。

昼は湯を沸かして、カニカマいりカプヌ(健康に気を使ってPRO仕様。カレーがお気に入り)を食べてご機嫌。

帰りのドライブでは眠気防止の眠眠打破(*´Д`)

そしてたまに旧知の釣り仲間とらーめんを食べながら反省会兼次回の作戦会議( ゚Д゚)

こんな感じで仕事はバリバリ、遊びもバリバリ楽しんでいます。
今週は釣りに行く度に次はあれもこれもと思い立ち、ついついamazonでポチって家に帰る度に「また何か届いてるよー」言われる今日この頃というお話でした <゜)))彡




皆さん今年のGWはいかがでしたでしょうか。
連休谷間を埋めれば10連休という方もいらっしゃって今週は休み疲れが出ていたりして??
私はというと例年通り実家の新潟へ行って母親と面会→ みんなでメシを食う→ スキを見つけて釣りに行く → 家族のご機嫌取りに軽井沢へパトロールと称して散歩にという感じでした。


ちょっとしたサプライズではまたウチの家族が「例の看板」の松ぺに行きたいというので松ぺに行って「例の看板」の写真を撮っていたら「マツコの月曜から夜更かし」にも出て我が家では有名人の松ぺの社長さんがちょうどクルマから降りて来て、「写真撮らせてもらってます」と言ったら「どうぞ、どうぞ、写真を撮ってください!その代わり私の手品も見てください!」とその場でマジックを披露してくれたこと(*´Д`)
御年80歳になられる社長さんが一見のお客さんにおもてなしのサービスがスゴ過ぎてやっぱり話題になるお店の社長さんはすごいなーと感心/感動しました。
私もおもてなしの”何か”特技を身につけないと!
でも手品は無理かなー
ではGW明けのブログまったりとスタート
*******************************************************
連休前にひと通り現場やモデルハウスを回って、急な風雨で危険な場所がないか、雨仕舞や養生がちゃんとされているか、施錠がされているか、ゴミが散らかりそうな場所がないか、チラシボックスが空になっていないか、など点検してまわっていたらエステートハウスのモデルハウス入口のドラセナに花が咲いているのを発見!(@_@)

 しかも種類が違うのか花の色も違ってキレイ♡
しかも種類が違うのか花の色も違ってキレイ♡
で、会社に戻って調べるとドラセナは別名「幸福の木」と呼ばれて、花は不定期に咲くのでとても珍しく見られたらラッキーと( *´艸`)
ここまでは良かったのですが、そのままにしておくと株が弱って枯れてしまう、枯れる前兆??みたいな記事もあってえええーって(;゚Д゚)
参考記事↓
https://flover-s.jp/Form/Story/shoku-butu-shurui/koufuku-no-ki/koufuku-no-ki-hana
連休中に枯れてたらどうしようと思いつつも、せめてGW中は咲かせておいて通りすがりの方にも楽しんで欲しいなと思いそのまま放置。
GW明けに花の刈り取りに行ってきました。
 ドラセナの花は葉の間から木の幹のようなしっかりした茎が出て、そこからさらに枝分かれして小さな花が無数に咲いています。
ドラセナの花は葉の間から木の幹のようなしっかりした茎が出て、そこからさらに枝分かれして小さな花が無数に咲いています。
我が家にも30年近くドラセナを植えていたのですが花が咲いたのは一度も見たことがなく、貴重な体験。
参考記事によれば花が咲く条件は以下の通り
ドラセナが花を咲かせる条件は以下の3つです。
- 7℃以下の気温
- 日光をよく浴びている
- 低栄養状態
暖房を入れる時期にはベランダに出す、日当たりのよい場所に置く、肥料を与えない、の3つの条件を整えることで、より花を咲かせる可能性が高くなります。
なるほど、ウチの場合は栄養豊富だったのかな??
会社に持ち帰ると確かに臭いが芳香というよりは強めで閉空間ではきついので玄関に置きましたがそれだけで2Fまで香りが漂うほどでした(でもいい香り)。

 良く見るとひとつひとつの花が王冠みたいな形をして可愛いんですよね~
良く見るとひとつひとつの花が王冠みたいな形をして可愛いんですよね~
その後も玄関にバケツに水を入れて挿して置いたら今週1週間はきれいに咲いてくれました。
今回は偶然の産物でしたが最近はロックガーデンでドラセナも多くみかけるようになったのでぜひ”幸福の花を咲かせようチャレンジ”をしてその貴重な花を愛でて香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
今週はこれだけ幸福の花を愛でたのだから、さあ来い!幸福!というお話でした(見られたことが幸福か( *´艸`))。




今年のGW今日からお休みという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当社も表向き(HP上)は今日から5月6日までGWとアナウンスはしていますが以前から予約をいただいているお客様や現在着工中の現場は稼働しています。
かく言う私もおかげさまで色々と案件がありまして、今週は通常通りの投稿となります。
さてこちらは今朝出がけに撮った自宅のホスタ達です。


 3月頃に苦土石灰と家のウラに放置していた物入で見つかったたい肥を撒いたのが良かったのか、雑草もモリモリでやや見苦しいかもしれませんが今年は今のところ絶好調です( *´艸`)
3月頃に苦土石灰と家のウラに放置していた物入で見つかったたい肥を撒いたのが良かったのか、雑草もモリモリでやや見苦しいかもしれませんが今年は今のところ絶好調です( *´艸`)
これ以外にも地球沸騰化対策で日陰に移植したビッグママとフランシスウィリアムスがこれから葉を広げるところなのでさらに楽しみです。
では今週もブログスタート
***********************************************************
今週は「消滅可能性自治体」のニュースが話題となりましたね。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20240424/1060016840.html
「自分の住んでるとこはどおかな。。。。」なんて確認された方もいらっしゃるのでは。
興味深いのは
”10年前、2014年に行われた同様の分析と比べると、県内の「消滅可能性自治体」の数は変わっていませんが、今回、新たに藤岡市、富岡市、板倉町が加わりました。
一方、高山村、大泉町、邑楽町は「消滅可能性自治体」を脱却しました。”
という記述。
リストから脱却した3自治体は10年前のこのレポートを受けてなんらかの施策を打ったのでしょうか??
また
”今回の分析では、2050年までの若年女性人口の減少率が20%未満にとどまっている自治体を「自立持続可能性自治体」と名付け、「100年後も若年女性が5割近く残っており、持続可能性が高いと考えられる」としています。
全国で65の自治体が「自立持続可能性自治体」と分析されていて、県内では唯一、吉岡町が該当しています。”
いわゆる”吉岡バブル”ですね。
当社でお家を建てていただいているお客様にも吉岡町は人気です。
同様にこれからお家を建てる方々は少なくとも「今日滅可能性自治体は避けたいな」と思うのではないでしょうか。
あくまで”今から未来を予測したところ”というレポートなので今後各自治体がこれに奮起してリストからの脱却を目指すことを期待しています。
個人的な見解(期待?)としてはコチラに期待です。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/320772
「吉岡バブル」の次は「伊勢崎バブル」来そうですね~
さてさて消滅可能性自治体めっちゃ多いやんというその一方でこんな報道も
https://toyokeizai.net/articles/-/738836?display=b
最近やたらとTVでも「群馬」いじられてますもんね。ウチの子も録画してメシ時に「群馬出てたよー」と見せてくれます(*´Д`)
ただこの記事がまんざらでもないなと実感するのが、当社でも「群馬最高!」「群馬に惚れました!」と他県、他国から移住希望のお客様が続いています。
自分がそこに住んでいるとあらためて魅力はと問われてもそれが日常なのでわからないものですが外から来た人にはその自然や人、物価、駐車場無料が当たり前、地震などの自然災害にも強くベイシアとカインズとワークマンとヤマダ電機とビックカメラとJINSメガネで何でも揃う!がとても魅力的なのかもしれませんね。
ここまではへーぐらいな記事ですが先週「こ、これは!?」と目を引いたのがこの記事
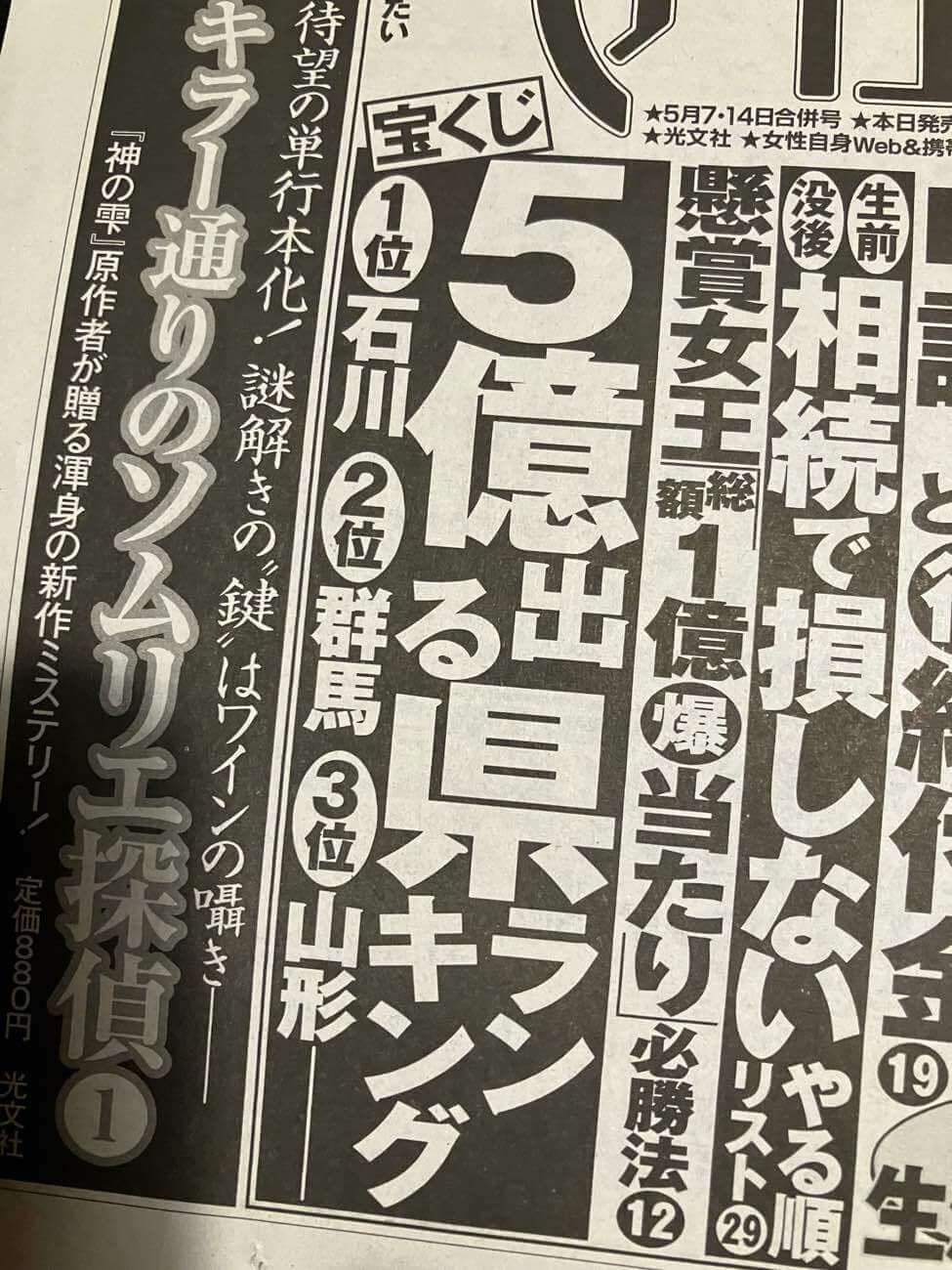
ここでも2位なんですね(*´Д`)
それはともかくよくこんなランキング思いつくなーと感心しました※でも雑誌は買わず
webでも載っているかなと検索したらなぜか福井新聞オンラインでこんな記事が
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1581012
くじの当選確率と場所ってほんとに関係あるんですかねぇ。。。
よく「当店で1億出ました!」みたいなカンバン見ますけど、ここで買えば「私も。。。」と思うんでしょう。
それにしても今はほんとに色んなデータを元にランキング記事が多いですよね。
統計的なデータに基づいて入ればまだいいのですが「おススメ」とか「人気」とかいうランキングは何らかの操作がされているのだろうと思いつつ私も食事やお出かけ先の参考に、お客様との話題作りにと見てしまいます。
という訳で今週はGW初日によろしければ群馬移住を考えてみては?というお誘いの投稿でした。
移住先の物件探しは当社にお任せください。英語でのご案内もギリ可です。
尚、来週5月4日はブログお休みとなります。
皆さまよいGWを!!




今年もロゴ入りポロシャツ支給しました。
2024モデルも昨年と変わらずユニクロのポロシャツで同じ品番をオーダーしたのですが定価が1000円アップしてましたΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
こんなところでも物価の上昇を感じますね。。。

幸いプリントの方は昨年と同じコストで出来ました。
ありがたいのですが逆に印刷屋さん大丈夫かな。。と同じモノづくりに関わる者として心配になる今日この頃です。
では今週もブログスタート
**********************************************************
2月が暖かったのでフライング気味にスタートした芝生ライフ2024
その後3月の冷え込みで芝の成長が進まずやきもきしていましたがここに来てようやく、今度は夏日が続くようになって色づいて来ました。

昨年貼った前橋江木のモデルハウスの芝が今日現在でこんな感じ。
GW頃には一応全面が緑になるのかな?
さすがに今年は最初から密度が違いますねー、いい感じです(*´Д`)

 こちらは当社高崎本社の前庭に貼った1年生。
こちらは当社高崎本社の前庭に貼った1年生。
上の写真のポスト前は一部昨年モデルハウスで余った芝が貼ってありますのでそこだけは2年生なのですでに青々としていますね。
今週はせっせと水撒きをして「早く伸びろー早く伸びろー」と念じています(*´Д`)
しばらく根付くまでは雑草も放置ですが早く一発目の芝刈りやりたくてうずうずしています。
昨年モデルハウスでやらかした軸刈りにならないように気をつけないと。
今週は暑さにカラダが慣れないので仮払い機回して1区画草刈りしただけで結構バテバテながらの投稿でした。

たくさんの「想い」が夢になって、はじめて真の価値あるものが生まれます。
お客様と気持ちをひとつにして、未来へ向けてカタチを想像していきます。

ひとつひとつ丁寧な家づくりで
豊かな暮らしを実現するお手伝いをします。
高崎テクノはお客様のニーズにお応えするために設計、プレカット、パネル工場とのネットワークを活用し、他社に先駆けて非住宅木造建築に取組んでいます。
AIを活用した物件提案から相続・土地活用のコンサルティングまで専門家ネットワークを駆使してサポートします。
新感覚の家づくり!「好きなものを4回選ぶだけ」。豊富なプランやオプションからあなただけの組み合わせを見つけよう!
工場・物流関係を中心に建屋の営繕+省エネで投資を抑えながら既存施設を永く活かせる提案をします。